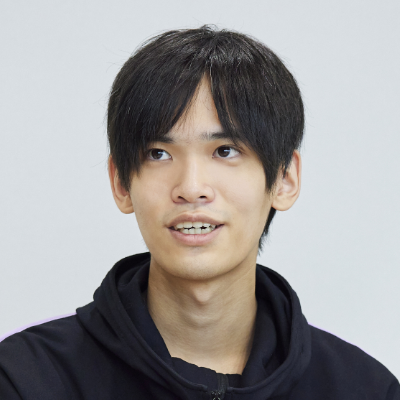2041年、「障がい者」の呼称を変更へ──。双子の松田文登さん、崇弥さんは、そんな未来を思い描きます。そして、その旗振り役に、2人が立ち上げた株式会社「ヘラルボニー」がなっていることも。
ヘラルボニーは、国内外の主に知的障がいがある作家たちとライセンス契約を結んでいます。作家が描くアートを用いてブランド「HERALBONY」の商品を開発。ネクタイや傘といった身近なものを販売するほか、駅やオフィスの空間プロデュースも手がけます。作品の使用料が、作家や作家が利用する福祉施設の報酬として支払われています。
このビジネスモデルは作家なしには成り立ちません。福祉の世界において、障がいのある人は「支えられる」側として語られがち。しかし、崇弥さんは「私たちが作家に支えられている。この逆転した構造を持つヘラルボニーが成長することで、障がいのある人への尊敬の文脈を世の中につくりたい」と話します。
2人の活動の原点は、4歳上の兄・翔太さんの存在。重度の知的障がいを伴う自閉症があります。翔太さんは2人と一緒に楽しく暮らしているのに、周りから「かわいそう」と思われたり、バカにされたりすることがありました。文登さんは「私たち双子の最終ゴールは、兄のような存在がありのままに肯定される状態をつくること」と語ります。
崇弥さんには最近、うれしい出来事がありました。講演会で出会った人が「ヘラルボニーのアートって、障がいのある人たちが手がけているんですね」と驚いた様子で話しかけてきたのです。百貨店でよく目にするので、純粋にお気に入りのブランドとして認識していたのだとか。起業して5年あまり。崇弥さんは「障がいの文脈とは関係なく、出会った瞬間に『格好いい』『素敵』と思わせる。そんなアートの力が伝わっていることを知り、すごくうれしかった」と言います。

「Let it be」
森 啓輔
そもそも、アートでビジネスを成立させることは簡単ではありません。「障がい者であることを売り物にするのはずるい」といった意見を聞くこともあるそうです。しかし裏を返せば、ヘラルボニーの商品を手にする人がそれだけ増えているということ。だから、意見が出ること自体、文登さんは「大きな進歩」と受け止めます。「今はまだ『出る杭』の状態ですが、『出過ぎた杭』になれば、こうした意見すら出なくなるはずです」。「クリスマスにプレゼントしたいブランド」のアンケートで、世界的なブランドと並んで選ばれる。41年にはそんな圧倒的な認知度を持っていたいと、2人は願います。
事業の成長に伴い、作家の報酬は21年からの2年間で8.7倍に増えました。年収が数百万円を超え、確定申告をする作家も複数生まれています。投資家を巻き込み、売り上げを伸ばして事業を成長させる。その結果は作家への憧れにつながります。
「異彩を、放て。」──。このミッションの下、将来的には、領域をアート以外にも広げていきたい。文登さんは「それは音の世界かもしれないし、食かもしれない。いろんな分野の『異彩』たちが挑戦するためのインフラになりたい」と話します。
2人にとって今の世の中は、障がいや多様性を何とか理解するために努力しているように見えます。さまざまな領域に放たれた「異彩」たちが、社会に憧れや尊敬を生み出す。その結果、「人とは違うこと、それ自体が価値であることを、社会が腹の底から受け入れられる状態に変えたい」と文登さん。崇弥さんは「『障がい者』という言葉自体が、どうしても欠落のイメージを連想させてしまう。そろそろ呼び方を変えるべきだという機運をつくる段階まで、ヘラルボニーを成長させていきたい」と考えています。