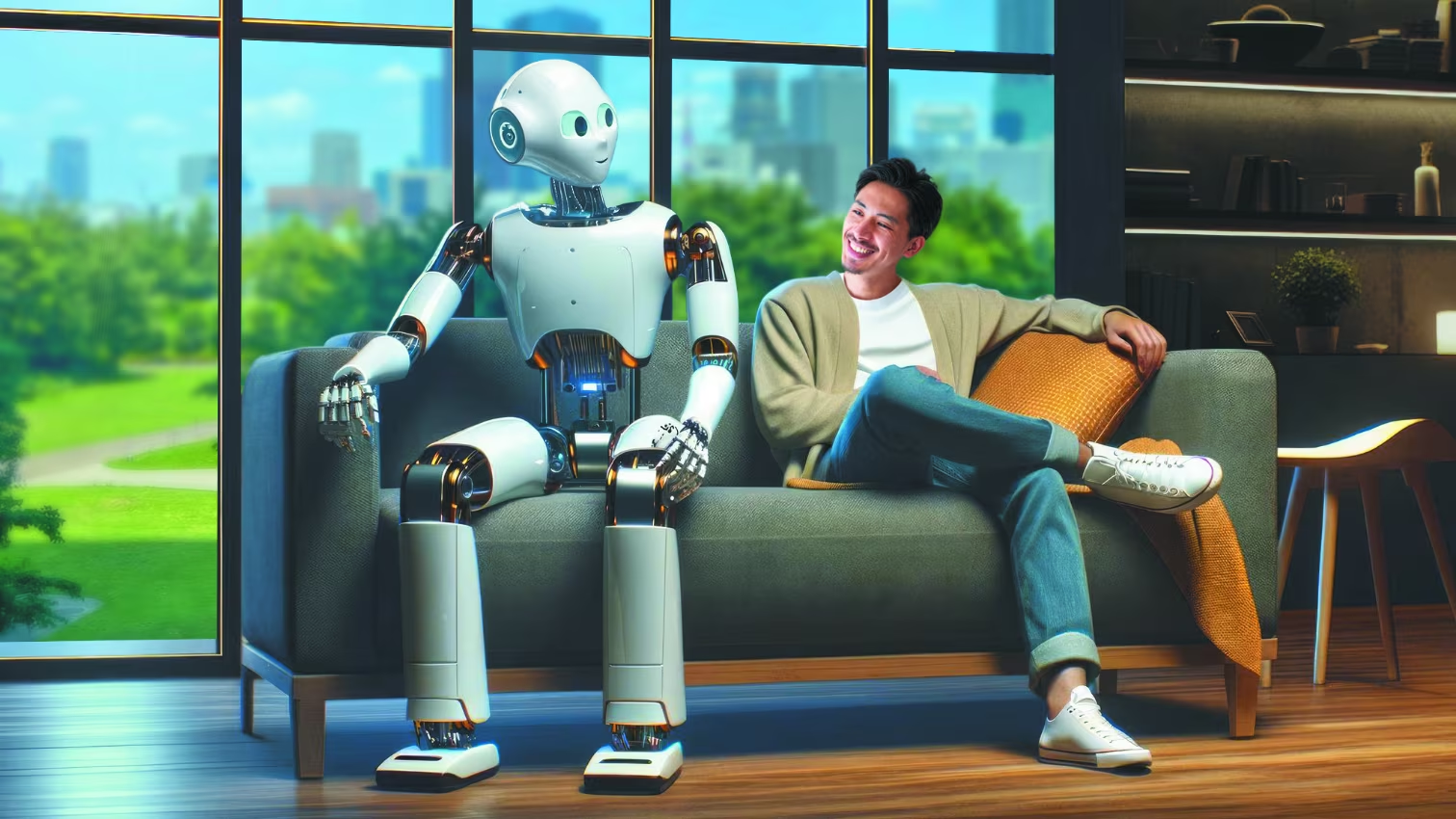内閣府はこどもの日に合わせ、「少子化社会に関する国際意識調査」の結果を公表した。「子どもを生み育てやすい国と思うか」との質問では、肯定的回答が過去最高の98%で、2005年度の調査開始以来、過去最高の世界1位となった。肯定的回答が過去最低の38%を記録した20年度から大きく上昇した背景には、保育・教育分野への手厚い人材配置に加え、国家資格である「子育てケアマネ」制度の創設・拡充が大きく寄与したとみられる。
98%はスウェーデンやフランスを上回る水準。日本では、2023年に婚姻数が戦後初めて50万組を下回り、出生数も80万人を割り込んでいた。少子化トレンドの反転のきっかけになったのが、同年4月に施行された「こども基本法」。子どものウェルビーイングを重視した未来に向け、国が大きく舵(かじ)を切った。特別会計「こども金庫」の予算も、24年時点で構想していた3.6兆円から、29年度には20兆円規模に。上積み分は主に保育士や教員、スクールソーシャルワーカーなどの保育・教育関係の人件費に充てられた。保育士の「配置基準」も先進国で最も手厚い「15対1」になり、対話型授業に最適とされる25人学級の導入、高校・大学の無償化も実現した。
さらに、30年度から国家資格である「子育てケアマネジャー制度」が始まり、全国の自治体に配置が義務づけられた。子育て支援に詳しい専門家の中川碧さんは「ここ10年の社会のありようを変えた」と評価する。「妊娠期から子育て期まで切れ目ないサポートを行うのが、子育てケアマネの役割。子どもが生まれる前から親の不安に耳を傾け、生まれてからも子どもの個性、特性や性格を尊重しながら、親も子も幸せになるために必要なケアを、当事者の声やニーズに丁寧に寄り添って届ける専門職です」とした。子育てケアマネの導入後、望まない妊娠の件数、児童虐待の件数は減少傾向に転じ、特に乳幼児の虐待死はゼロになった。
経済協力開発機構(OECD)が40年に実施した、世界各国の15歳を対象とする学習到達度調査(PISA)では、子どものウェルビーイングの指標とも言われる「生活満足度」が初めて世界1位に。国立社会保障・人口問題研究所の最新の調査では、夫婦の理想の子ども数は「3人」に。41年の合計特殊出生率は人口置換水準の2.07には及ばないものの、1.8程度まで回復し、25年ぶりに出生数は増加トレンドに転じる見込みだ。設備投資による長時間労働からの解放、若者の実質賃金の上昇、ジェンダー格差の是正も、婚姻数や出生数の増加を後押しした。
(取材協力・監修=日本大学文理学部教授・末冨芳さん)
末冨芳さんのインタビュー
子育てをリスクにしない国に
賃金改善、保育・教育人材の確保 国は思い切った戦略を
空想記事「『子育てしやすい国』世界一」は、日本大学文理学部教授で、政府に対して「子どものウェルビーイング(幸せ)」を重視した提言を続ける末冨芳さんへの取材を参考に作成しました。末冨さんに、記事の背景にあるテーマを聞きました。

少子化の要因は低賃金化を背景とした「非婚化」

日本の場合、結婚して子どもをもつ人が多いことから、少子化の一番の原因は「非婚化」だと言われています。なぜ結婚する人が減ったのか。その理由は、「若者の低賃金化」にあると末冨さんは話します。
「1990年代前半から2000年代前半の長い就職氷河期の間に、働いても給与の安い若い世代が増えました。1997年と2017年の所得分布を見ても、300万円台を稼ぐ20代、400万円台を稼ぐ30代、どちらも1997年より2017年の方が少なくなっています。この20年で社会保険料や年金負担率も上がっていますから、手取りはさらに減っているのが現状です」
もう一つ、末冨さんが非婚化の理由に挙げるのが、「長時間労働化」です。「男性も女性も長時間働く人が増え、結婚したくても出会いの時間もなく、結婚しても家事育児の負担は女性の側に重くのしかかってきました。若い世代が結婚・子育てに前向きになれないのは無理もありません」
少子化が進むと、労働力不足が懸念されます。AIによる代替ができない分野、例えば、医療や保育・教育、建設の現場などで人材が不足すると予測されています。
未来を変えるためには、まず「若い世代の手取りを増やすこと」。「仕事を効率化するための設備投資を行って長時間労働を緩和し、人手が必要な分野を予測して、重点的に人材を育てる必要があります。その上で、若者は社会保険料や年金を一定期間無料にして30歳から徴収開始にする、恒久的に大学までの授業料を無償化するなど、国家が思い切った手を打つべきです」
「子どものウェルビーイング(幸せ)」を重んじる国へ転換を

内閣府が公表した少子化社会に関する国際意識調査(2020年度、20~49歳の男女が対象)では、「子どもを生み育てやすい国だと思うか」の肯定的回答は38%。これは、同じ調査をしたドイツ(77%)、スウェーデン(97%)、フランス(82%)と比べても突出して低い数字でした。
どうしたらこの状況を変えられるのでしょうか。末冨さんの答えは、「子育てをリスクにしない国になればいい」。そのためには、「子どものウェルビーイング」に重きを置いた政策が重要になってきます。「少子化対策に成功していると言われるスウェーデンやフランスは、大学までの教育費は無償。子育て世帯は税制上も優遇されます。国として、子ども若者への投資を惜しまない姿勢を示すことが重要なんです」
日本では2023年4月に「こども基本法」が施行され、同法に基づき、「こども未来戦略」「こども大綱」が定められました。「子どものウェルビーイング」を重んじる未来に向けて国が舵を切ったことは、「評価できる」と末冨さんは話します。「あとは実際どれだけできるか。2025年度に創設された、こども・子育て支援のための特別会計の予算は3.6兆円ほどで、これでは全然足りません。将来的には20兆円、40兆円へと増やしたいですね」
末冨さんが引き合いに出すのが、介護制度です。「高齢者にかけられる予算は年間83兆円あるのですが、お金をかけているだけあって、世界的に見ても日本の介護制度は高い水準にあります。その子育て版の仕組みを作れないかなと思っているんです」
子どもひとり一人の声に耳を傾け、幸せを考えるのが大人の役割

介護の現場では、ケアマネジャーが要介護者に関するあらゆる相談に乗ります。「この人はどんな性格で、本人や家族は今はどういった状況なのか」「どんな暮らしをしたいのか」などを丁寧に聞き取り、必要な支援やサービスにつなげてくれるのです。
「そんな風に、妊娠期から子育て期まで切れ目なく、子どもの最善の利益を考えて寄り添ってくれる子育てケアマネジャーがいてくれたら心強いですよね。子どもが何か病気や障害を抱えていたとしても対応の相談に乗ってくれて、親が仮に離婚することになったとしても子どもの今後を一緒に考えてくれる。日本のどこで生まれても、その子と家族の幸せをサポートしてくれる専門職は、絶対に必要だと考えています」
20~40兆円の予算を使って、全国に子育てケアマネを拡充。さらに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーも全校に配置します。4~5歳児の保育士の「配置基準」は「子ども15人に1人」に、小中学校では「25人学級」が当たり前。高校教育の内容も、子どもの自由度の高い学びに変えます。「大人が子どもの声に耳を傾けて、子どもの幸せを考える国になっていけば、今30万人いる不登校の子どももかなり減るはずです」
家族だけでなく、国や社会からも大切に育てられた人は、自分も、自分の周りの人々も大切にする人に育つと、末冨さんは言います。「自分や自分以外の人々を大切にする“ソーシャルエモーショナルスキル”は、人類から失われてはならないものです。子どもや子育て世帯が幸せに暮らせる国になったから、結婚したい、子どもを生みたいと思っている人はそれが叶えられるようになって、結果として子どもの数が増えつつある。そんな未来につなげていきたいですね」