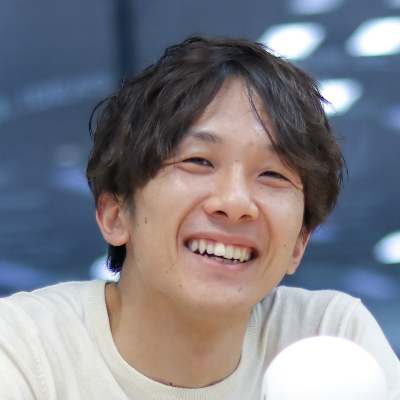音楽プロデューサーの小林武史さんは「未来」を見据えた行動を続けてきました。2023年に千葉県で立ち上げた「百年後芸術祭」を舞台に、「アート」「テクノロジー」「音楽」「食」を通して人々と「100年後」をつくっている取り組みもその一つです。
自分は存在せず、他者が生きる世の中を想像することは、ややもすると難しいかもしれません。でも、小林さんは、そうした未来の感覚は「持つことができる」と言います。「来年は『昭和100年』。そう考えると100年という道筋は見通すことができるし、自分の感覚として持てると思うんです」。過去から現在までの道筋を思い返してみると、これからの未来を想像することはそこまで難しいことではない、と小林さんは考えます。
加えて、誰もが無視できないレベルの気候変動を例に挙げ「5年後、10年後。もしくは20年後、50年後に対してこれだけ意識的にならざるを得ない時代は今まで絶対なかった」とも。それを推測、検証していくための科学技術の進歩も大きな後押しになっていると感じています。

未来を考えるときに媒介となるのが「自然」と「テクノロジー」。「自然を媒介したほうが人間は生きやすい。人間も自然の一部なんです。命とはそもそもそういうものだと思うのですが、今度はそこにテクノロジーが加わるでしょう。アートや音楽の分野では「入力する色々なコマンドによって生成AIなどで作られた大量の選択肢から人が選び取るプロセスを経て、人間同士で作るのとは違う表現が生まれる」と言います。
小林さんが率いる新たな形のバンドには、新しい表現を作り出すために音楽、映像、テクノロジー、科学などさまざまな分野のアーティストやクリエーターが集まりました。ライブアートパフォーマンスでは世代を超えたアーティストが共演し、空にはドローンによって彩られた満天の星空が。
「音楽と融合したドローンパフォーマンスもテクノロジーによって生まれるものの一つ。過去の歴史からもわかるように、テクノロジーは使い方に気をつけなければいけない側面があります。ドローンで言えば殺人兵器にもなりますよね。でも、それを介在させるからこそ生まれる表現を私自身、楽しみにしています」
太陽光の循環を 未来に紡ぐ「場」づくり

環境プロジェクトへの低利融資をするために作られた非営利団体「ap bank」、「社会」と「私たち」をつなぐ「場」としての「ap bank fes」、東日本大震災の被災地での芸術祭「Reborn‒Art Festival」、農業と食とアートの複合施設「KURKKU FIELDS(クルックフィールズ)」。
本業の「音楽」にからめながら、持続可能な未来のために多くの「場」を立ち上げてきた小林さん。根底には、人間が生み出したテクノロジーによる核の脅威の矛盾、脅かされる自然や環境に対する危機感があります。100年後も、さぞかし暗い未来を描いているのかと思いきや「悲観的にはなっていません。楽観的なぐらいです」。純粋に「希望を持って明るい未来をつくっていこう」というわけではありません。問題となる「毒的な要素」はあるものの「それは乗り越えていくべきもの」と力を込めます。
「クリエーティビティー」と 「イマジネーション」が鍵

原動力となるのが「クリエーティビティー」と「イマジネーション」。人はさまざまな工夫をすることができるし、わかっていないことについても想像できる。
「KURKKU FIELDS」での農業も「クリエーティブ」。ここでは従来の「耕す農業」ではなく「耕さない農業」である「不耕起栽培」に取り組んでいます。不耕起栽培は、土壌に含まれる炭素が攪拌(かくはん)によって空気中に放出されるのを防ぐため、温室効果ガスの削減効果が見込まれます。食料自給率が低い日本で「依存」から脱却し、そうした工夫をしながら自給することに喜びを見いだす「次世代」の担い手の姿に小林さんは希望を見て、私たちはすでに「平和な未来に向けてリーチしている」と話します。
41年の未来は「国家間の扉が開き風通しがよくなることで、国を超えた連携が進み、集合体としての『世界』が物事を決めていくような世の中になっている」というのが小林さんの考えです。
「完全に『利己』で生きるなんてあり得ない。誰かが何かをすると必ず誰かに影響が出るし、しわ寄せが出る。それを自己責任と言うのは乱暴な気がする。善意的な意味ではなく、利己と、誰かのためを思う利他はつながっている。『利他』があたり前なんです」。人と人、国と国、自然環境──あらゆるものが「循環」する「場」づくりをしてきた小林さんの軸はそこにあります。