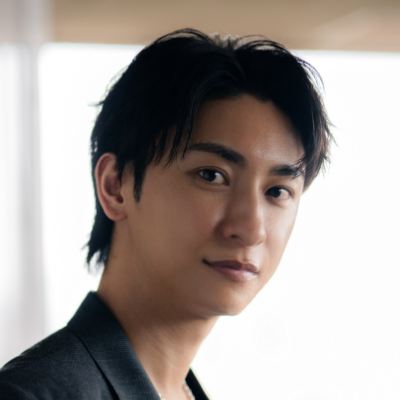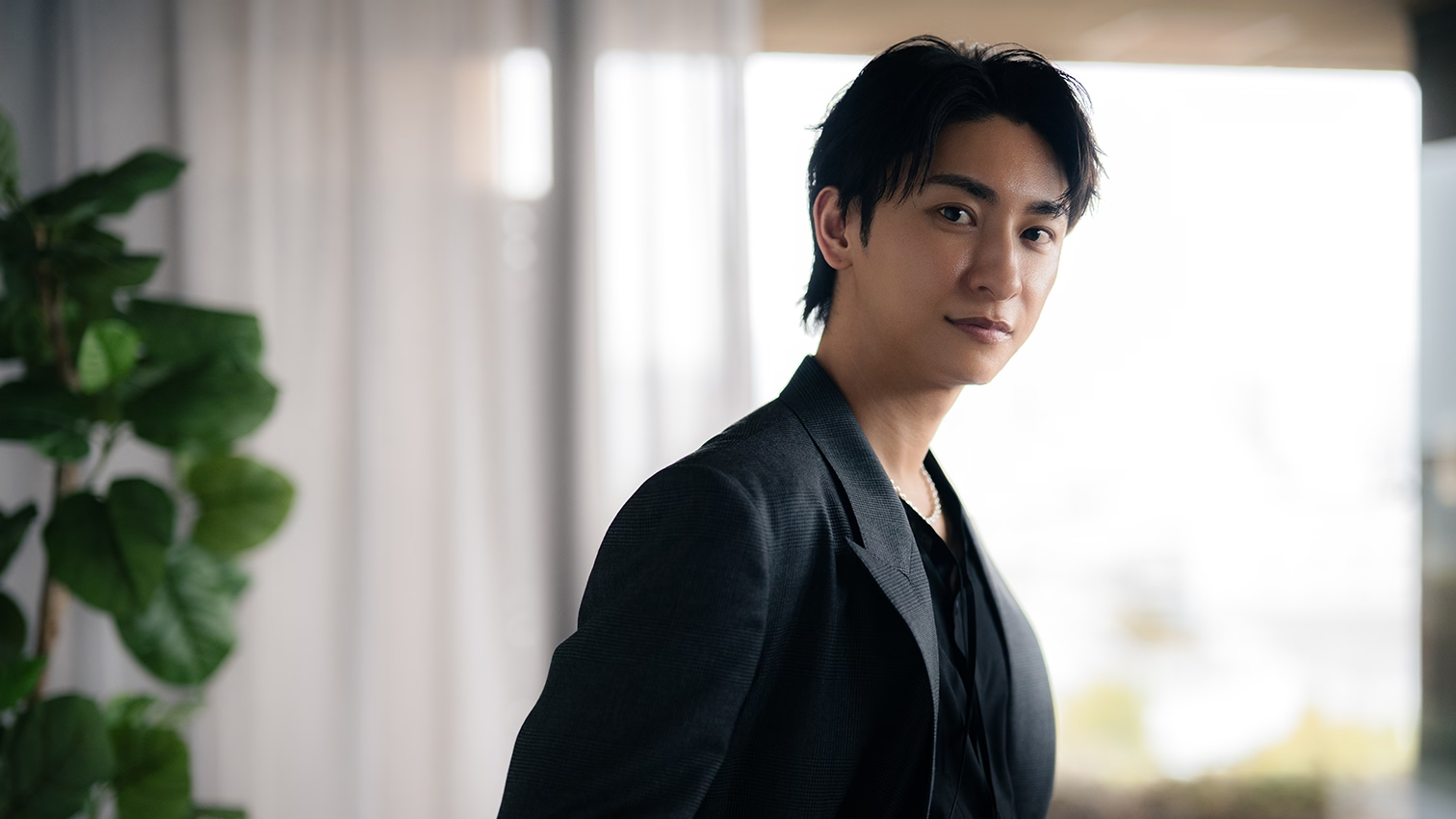「うそのようではございますが」。エープリルフールの4月1日、東京の新宿末廣亭で開かれた真打昇進披露公演で、落語家の林家つる子さんがしきりに会場の笑いを誘っていました。3月に最上位の真打に昇進。入門順に昇進するのが慣例ですが、つる子さんは11人の先輩を抜いての昇進で注目が高まっています。
男性目線で語られてきた古典落語を、脇役の女性を主人公に描き直して演じる取り組みが評判になりました。名作「芝浜」や「子別れ」という演目では「どうしても噺(はなし)が亭主を主人公にして進んでいく。おかみさんが描かれていない場面ではどういう気持ちで、どんな行動をしていたのかが気になっていました」とつる子さん。
「落語を侮辱している」といった批判を受けた半面、女性客からは「男性社会に合わせようとつらい思いをしてきたけれど、新しい道を切りひらく努力をしてもいいと思えて心が軽くなった」との感想も。
「代弁者と言うとおこがましいですが、史実や歴史を踏まえて『この時代に生きた女性はこういう気持ちだったかもしれない』と、現代の女性にも共感できる思いを抽出していきたい」と意気込んでいます。

つる子さんが一番大切にしたいのは「江戸時代から伝わる古典落語」だと話します。一方で「『噺家は世上のあらで飯を食い』と言うように、その時代のことをずっと(落語の前置きである)まくらやネタに取り入れてきた」と語ります。「古典落語が生まれた時代にはその当時を生きた人が新鮮な噺として聞いていた。今の時代に合わせた噺が生まれるのは自然なことです」。つる子さんはスマホなどの現代の話題を盛り込んだ新作落語などを例に挙げます。
最近はメタバース(仮想空間)での落語にも挑戦し、ウケがよかったと手応えを感じたそうです。ただ、若者が落語に触れる機会は多いとは言えず、ファンをどうやって増やすかが課題と考えます。「実は伝統芸能の中でもかなりカジュアルな分野で親しみやすい。現代の人の心にも寄り添ってくれる。知らずに終わるのはもったいない」
短いインパクトのあるコンテンツがはやる時代。それでも、ふらっと寄席に行き、噺家の語り口から想像を膨らませ、自分だけの空想の世界に浸る。そんな時間を若い人たちに経験してほしいと願います。
その思いが通じて、共感が広がったら。2041年に落語が生き残るどころか、新聞に「寄席、連日満員御礼 落語が大ブーム」という見出しが躍るかもしれない。芝浜のオチは「夢になるといけねえ」。決して夢では終わらせないと誓います。